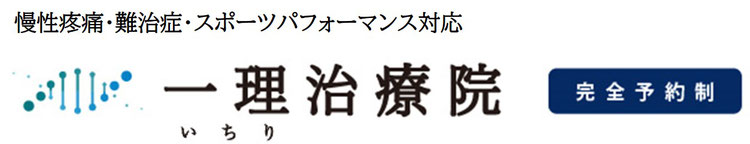頭・首・顎(あご)の症状
頭痛

このようなお悩みはありませんか?
☑ガンガンズキズキする拍動性の頭痛
☑重く締め付けるような頭痛
☑30分から数日、頭痛が続く
☑頭と顔の片側で常に鈍い痛みを感じるまたは両側で感じる
☑胃のむかつきや吐き気、嘔吐がある
☑めまいがする
☑明るい光を見ると頭が痛い
☑音が聞こえると頭が痛い
☑天候の変化によって頭が痛くなる
☑強い香りで頭が痛くなる
☑ホルモンの変化により頭が痛くなる
(症状の概要)
頭痛は、二日酔いや疲労などによって起きる一次性頭痛と脳卒中など何らかの病気が原因の二次性頭痛に分けられます。
ただし、頭痛の原因はさまざまで特定できないこともあります。
(種類)
●片頭痛
脈を打つようなズキズキする痛みが、頭の片側を中心に起こります。脳内血管の収縮、その後、急速な膨張を伴う遺伝的神経学的状態です。頭の中の血圧が急激に上昇し、耐え難いほどの痛みを引き起こします。痛みが起こる前兆として、視界にキラキラと光るものが見える場合もあります。
●緊張性頭痛
頭全体が締め付けられるような頭重感と頭部両側が痛む頭痛です。多くの場合、肩や首のこりを伴います。時には、後頭部から首筋にかけて圧迫されるような痛みや、めまいやふらつき、身体のだるさなども伴います。
●群発性頭痛
強烈な痛みが目の周りから後頭部にかけて広がり、目の奥に激しい痛みが起こります。痛みの他にも結膜充血、鼻づまり、発汗といった症状が現れます。片頭痛とは異なり、男性に多いことも特徴の1つです。
●頸性頭痛(首から起因する頭痛)
痛みは頭に感じられますが、機能障害は首に起因しています。これらの頭痛は首の上部3つの椎骨に起因します。特定の動きまたは持続的な姿勢は、首の関節、筋肉、靭帯、椎間板および神経に緊張または圧迫を引き起こす可能性があります。
(一般的な原因)
●片頭痛に関して
ストレスや疲労が関わっていることが多く、女性ホルモンの影響も発症の要因として挙げられています。
その他にも天気や気圧の変化、入浴や飲酒といった行為で痛みが誘発されるケースもあります。
●緊張性頭痛に関して
身体的ストレスと精神的ストレスなどで、筋肉がこわばることが原因と考えられています。
●群発性頭痛に関して
原因は詳しく分かっていませんが、目の後ろにある頸動脈の血管が拡張することにより発症すると考えられています。アルコールが引き金となることもあります。
●頸性頭痛に関して
首の上部に過度のストレスや負荷をかけることによって引き起こされます。
むち打ち症や鈍的外傷などで発生する場合もあれば、姿勢が悪い状態(長時間のPCなど)が続くと徐々に増加する場合もあります。
(改善するための手段)
●ストレッチ
●手技療法を受け、身体のバランスを整える
●予防的な薬を服用する
●栄養価の高い食事をする
●定期的な運動
●水分補給をする
●十分な睡眠を取る
●ストレスレベルを低く保つ
●アルコールを避けるか制限する
●専門医に診てもらい検査をする
首の痛み

このようなお悩みはありませんか?
☑仕事をすると首が凝る
☑スマホを使っていたら首が痛くなる
☑キーボードの入力作業が多く首が痛い
☑首だけではなく腕や肩、手の痛み、しびれ、動かしにくさがある
☑首の向きや腕の動きによって痛さが違う
☑首を回すと痛い
☑ストレスとともに増加する首の筋肉の緊張
☑頭痛の痛みを引き起こす首の痛み
☑突然の衝撃により痛みが発生(むち打ち症など)
☑枕が合わず起きたら首が痛い
☑めまいや吐き気を伴う
☑肩こりがある
(症状の概要)
首の痛みは交通事故、姿勢不良などがありますが骨格の異常からくるものが大半です。現代の仕事や趣味、遊びには首や肩に負担を掛けるシーンが多いことが関係しているといわれています。
首が痛むので首の施術のみされる方がいらっしゃいますが、身体全体を整えバランスを整える必要があります。
急性の痛みは通常、首の緊張やスポーツによる怪我などの急性の怪我に対する即時の反応として始まります。通常、4週間未満続きます。
慢性的に痛みは一般的に徐々に始まり、特定可能な根本的な原因がある場合とない場合があります。痛みは通常、少なくとも3カ月続くと慢性痛と見なされます。
(種類)
●筋肉の緊張(肩こり等)
首や肩周辺の筋肉の疲労により血流が滞ることが挙げられます。肩や腕まで、痛みやコリ、だるさなどが生じることがあります。
●むちうち症
自動車事故に巻き込まれた人々によく見られます。車が後ろからぶつかったり、他の物体に衝突したりすると、首が激しく前後に動きます。
頚椎の捻挫は、首・肩の痛み、首の可動範囲の低下これらの症状は状況により根違い、むち打ちと呼ばれることもあります。
●頚椎のズレ
頚椎の関節部分がズレた状態での可動範囲の低下、神経的症状の発生(痺れ、頭痛など)が起こることです。
●頚椎ヘルニア(神経痛根)
30~40歳代の世代に多く発症していると言われています。頚椎関節からは各エリアに行く神経が出ているのですが、これが椎間板の突出により圧迫され、手、腕、時には肩への痺れ、痛みが発生します。40歳代後半、50歳代以上ではほとんど起こりません。これは、年齢が上がるにしたがって、椎間板の水分量が低下するために、椎間板自体の突出確立が低下するためです。
●後頭神経痛
頭皮や筋肉にある神経が原因で後頭部に頭痛が起こることです。後頭部の頭皮にピリピリ・チクチクするような痛みがあらわれます。痛みを感じる長さには個人差があります。また、頭を押さえると痛みを感じることもあります。
主な症状は、後頭部や耳の後ろが痛くなることですが、首の付け根に強烈な痛みを伴うケースもあります。痛みはすぐに治まることもあれば、繰り返し生じることもあります。
●頚椎不安定症
首の関節の過可動(動き過ぎ)の状態を示しています。よくある症状として、首をポキポキ鳴らしたりする状態です。
●脊柱靭帯骨化症
背骨の骨をつなぐ靭帯が厚みを帯び、骨化してしまう疾患です。それにより首の痛みの症状が出ます。
●斜頚
首の傾きがやや強い場合はこの診断がされます。首の周りの痛みが非常に多いです。首の横への傾きと旋回が複合で起きている状態を示します。
●関連痛
痛みがその原因以外の場所で出て、神経根の炎症が原因でない場合、それは関連痛と呼ばれます。通常、深く痛みを伴うけいれんおよびズキズキする感覚としてあらわれます。
関連痛は通常、体の片側だけに感じられますが、両方にある場合もあります。
●頚椎症
首の障害で最も多くみられ、特に50歳以上の中高年層に多く発症しているといわれています。
(一般的な原因)
●筋肉の緊張(肩こり等)に関して
精神的緊張や過度のストレスから痛みが生じることがあります。その他、まれではありますが頚椎に細菌が感染してしまった場合、首の痛みや発熱などの症状が起こることがあります。また、がんの転移などの頚椎に細菌が感染してしまった場合、首の痛みや発熱などの症状が起こることがあります。
●むちうち症に関して
これにより筋肉や靭帯が伸びて緊張が起こります。軟部組織の損傷と呼ばれ、こわばりや痛みを引き起こす可能性があります。また、むちうち症は、椎間板ヘルニアなどの構造的損傷、激しい動きによる過度の伸展による神経損傷を引き起こす可能性があります。
●頚椎のズレに関して
比較的軽い症状でも頚椎が原因で、肩こり、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴り等の症状も挙げられます。
●頚椎ヘルニアに関して
加齢などにより頚椎の椎間板そのものが変形した場合も、神経が圧迫され同じような症状を引き起こすことがあります。
神経痛は、頚椎の神経根が炎症を起こし、神経に沿って肩、腕、手に広がる痛みを引き起こす場合に発生する可能性があります。神経痛根が頚椎に起因する場合、通常、骨棘(骨のトゲの事)又は頚椎椎間板ヘルニアと呼ばれる骨の異常増殖によって神経根が炎症を起こした場合など、脊椎の変性が原因です。
●後頭神経痛に関して
後頭神経痛の原因は血管の圧迫やけが、頭や肩の手術などさまざまです。
●頚椎不安定症に関して
原因として、首の関節のズレや同じ首の動きを何度も繰り返すなどがあげられます。
痛みの場所は過可動を起こしている部分ですが、その痛みの原因は動きの低下した関節が引き起こしています。
●脊柱靭帯骨化症に関して
明確な原因は分かっておりませんが、骨化により脊髄が圧迫されてしまうと、首の痛み、手足のしびれなど、頚椎症と同じような症状が生じます。
●斜頚に関して
先天的にこの状態の方もいますが、症状が後天的な場合に限り施術が有効です。
頚椎での複数個所のズレによる傾きが発生している場合が多く、関節の可動範囲の復元と周囲の筋肉組織の施術を同時に行うと傾きの減少が見られます。
●関連痛に関して
関連痛がどのように発生し広がるかについてのメカニズムはまだ研究されています。たとえば、トリガーポイント(筋肉の圧痛または過敏性の部分)が圧迫されると、痛みの症状は体の他の部分に関連する可能性があります。ただし、トリガーポイントがどのように発生するかおよびその痛みのパターンが予測不可能かどうかについて医学会では確固たる合意はありません。
痛みは、心臓(心臓発作中)や顎(顎関節)など、さまざまな方法で首を指すことがあります。逆に、首の症状は、身体の他の部分に関連痛、最も一般的には頭痛、肩の痛み、または背中の上部の痛みを引き起こす可能性があります。
●頚椎症に関して
加齢などにより、椎間板の柔軟性が衰えると、頚椎も少しずつ変形しやすくなります。すると首に痛みが生じ、腕につながる神経が圧迫され、しびれや手が動かしにくいなどの症状が表れます。
改善するための手段
●手技療法を受け、身体バランスを整える
●予防的な薬を服用する
●ストレスレベルを低く保つ
●専門医に診てもらい検査をする
●自分の首の高さに合った枕選びをする
●ストレスを溜めないようにする
顎の痛み

このようなお悩みはありませんか?
☑あごが痛む
☑口が開かない
☑あごを動かす音がなる
☑硬い物が顎が痛くて食べられない
☑腕や指の痺れ、めまい、片頭痛、肩こり、首や肩などの痛み
☑目、耳、鼻、舌などに不快感や違和感がある
☑顔が歪んできた
☑片方だけの歯が削れてきた、または片方の歯だけぐらついてきた
(症状の概要)
顎は複雑な形状と多くの機能を持っており、筋肉と関節、神経が集中して下顎を支えています。食事や会話の際にはそれらが連動して機能しますが、この顎の関節やその周辺部分に痛みが出たり動かしにくくなったりするのが顎関節症です。
主な症状としては、口を開いた時に顎関節や顎の筋肉に痛みを感じたり、顎関節から音が鳴ったりします。
顎関節症の痛みは、顎関節の痛みと咀嚼筋の痛みに分かられ、そのいずれか、あるいは両方が痛みます。口が開けづらくなる要因としては、顎関節内部の関節円板(圧力分散のためのクッションの役目を担っている繊維がまとまった組織)がずれて関節の動きを妨げている、あるいは咀嚼筋の痛みで顎が動かせないことが挙げられます。
(種類)
●咀嚼筋痛障害
あごを動かす筋肉の痛みを主な症状とするものです。
●顎関節痛障害
顎関節の痛みを主な症状とするものです。
●顎関節円板障害
顎関節の中の関節円盤のズレが生じるものです。(関節円盤とは顎関節の骨と骨の間にあるクッションの役割をしている組織です。)
●変形性顎関節症
顎関節を構成する骨に変化が生じるものが含まれています。
(一般的な原因)
●食いしばり、歯ぎしり
●噛み合わせの不良
●顎関節の構造上の問題
●ストレスや不安からくる顎の筋肉の緊張
●首の構造上の問題
●頬杖
●片側の歯での噛み方の癖
●うつ伏せ寝の習慣
●猫背、背骨や首のバランスの悪さ
●スマートフォンやPCの長時間に及ぶ操作
改善するための手段
●歯の食いしばりに気付いたら上下の歯に隙間をつくる(マウスピース等)
●片側の歯だけで噛まずに両側の歯で噛むようにする
●手技療法を受け、身体バランスを整える
●頬杖をつかないように気を付ける
●十分な睡眠を取る
●マッサージをして筋肉の緊張をとる
●ストレスレベルを低く保つ
●歯科医院で咬合調整をしてもらう
●痛みの強い部分への遠赤外線のレーザー治療、ごく限られたケースでの手術を受ける
●開口訓練を行う
●炎症を抑えるために痛め止めを服薬
●うつぶせ寝に気を付け体位を変える
●スマートフォンやPCを操作する時は作業の合間に休憩時間をはさみ、体への負担を減らすようにする
●硬い食品の咀嚼や長時間の咀嚼をやめるように気を付ける
当院の理学療法士は、改善するための方法をより詳細に、わかりやすく指導することが可能です。
頭痛・首の痛み・顎の痛みの問題を解決するための最初のステップは、「原因」を見つけることです。
当院では、姿勢や歩き方、すべての背骨の動きの程度といった全体像をみることで、頭・首・顎にどのようなストレスが加わり、痛みを引き起こしている問題を特定していきます。特に、頭痛や首の痛み・顎の痛みを繰り返している人は、骨盤や脊椎の歪みがないか、注意深く調べることが大切となります。
当院では、手技療法と運動療法を合わせて行うことで、頭痛・首の痛み・顎の痛みの原因となる脊椎のズレや柔軟性が欠如して固定された部分の蓄積された緊張をリラックスさせ、再調整をします。
慢性化した頭痛・首の痛み・顎の痛みに苦しんでいる、これから改善していきたいと思われる場合は、田中ケアラボのスタッフに遠慮なくご連絡してください。